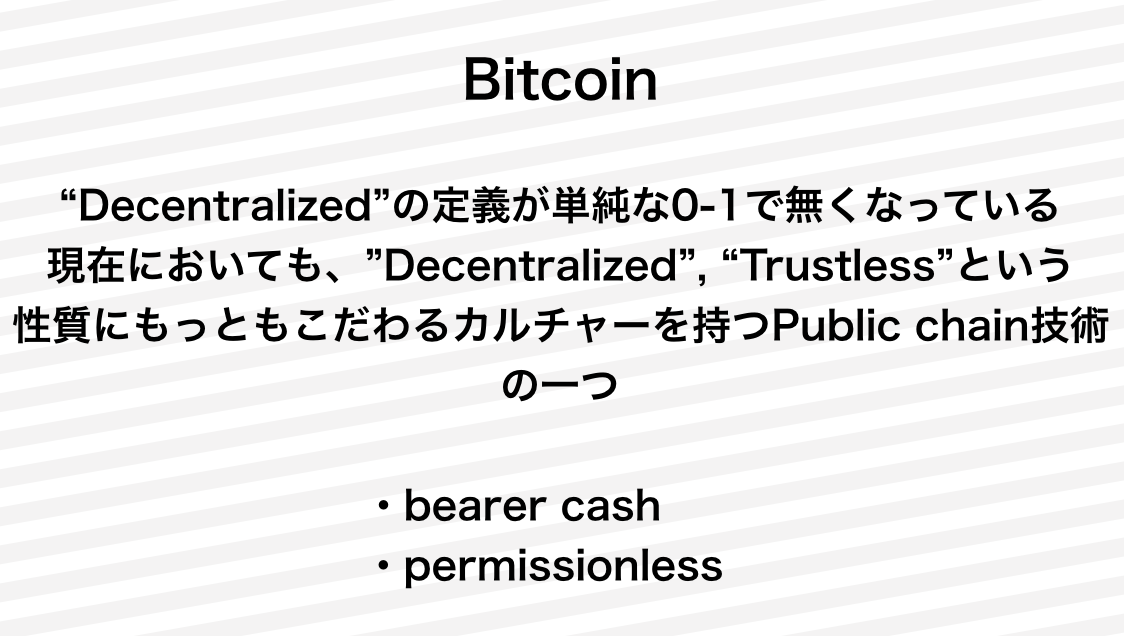超ひさびさの更新
春にダウンした後、原因もはっきりして体調回復したので半年以上ぶりにビットコイン関連の状況をキャッチアップしたのだけど、以前とはまったくことなる状況になっていてかなりのインパクトを受けたのでブログを更新してみることにした。ここからいくつかのエントリーは書きなぐりで全然検証してないので後で変更する可能性大。
このエントリー1については数年前から自分が思っていたことで次のエントリーのための文章。
以下のFidelityのレポートが前提知識として良くまとまっているのでリンクを貼ります。
2022年にニューヨークに2週間ぐらい滞在した時は、ブロックチェイナーだらけでビットコイン関連の人は非常に少なくなっていて、 話す人は皆、「ビットコインは消費電力が…」みたいなことを言っていた。 (その直後オースチンに一カ月滞在した時は、「ブロックチェーンは意味なくてスキャムだらけ」という人が沢山だった。同じ国とは思えないぐらい考え方が違う) このレポートを初めて見た時は、Fidelityは誰でも知っているニューヨーク金融の超大物プレイヤーだけどそれなりに理解していて少し驚いた記憶が。
余談だけど、ニューヨークで沢山のスマコンチェーンコミュニティの人とお茶したり食事したりして色々聞いたけど、 当時から「伝統金融の人達はメディアでは暗号資産系のことを批判するけど、実態はめちゃくちゃ協力的」という話を色々聞いていた。 あるDAOプロジェクトでは、ウォール街金融のブロックチェーン業界団体で名前が載るような人が重要な仕事をしていたりしていた。 こういうのがグローバル金融の人達。日本だとメディアや表向きの意見を信用してしまうけど、はっきり言ってそんなところに本音は無い。
このレポートの中で今後の発展について二つのストーリーがあり得るという感じで紹介されている。
■ストーリー1 マルチチェーン
 ビットコインは貨幣材としての地位を確立し、他のユースケースはEthereumブロックチェーンが使われてブリッジされる
ビットコインは貨幣材としての地位を確立し、他のユースケースはEthereumブロックチェーンが使われてブリッジされる
■ストーリー2 勝者(ビットコイン)総どり
 ビットコインが標準ブロックチェーンとなり、多くのアプリがその上に作られる
ビットコインが標準ブロックチェーンとなり、多くのアプリがその上に作られる
自分の考えはこの1,2とも微妙に違っていて、アプリケーションの多数はストーリー1のようにEVMチェーンで作られるのだけど、そちらは規制が作られてしまった後は、結局クラウドもしくは多数のコンソーシアムチェーンに移動していく。一部のDecentralizedが重要なアプリはストーリー2のようになるというもの。
それは、Public chainは維持コストが高いのでトークン値上がりが穏やかになった後は、よっぽど必要性があるもの以外はペイしないのではないかというのが理由の一つ。 (最近は、Rollup等でコスト安くできるというスタンスなんだろうけど、自分はそこについては詳しい知識がないので言及しない。) あり得る反論はEthereumに多数の証券、債券、様々なものが載って流動性を供給すると言うものだろうけど、今のところはそうなっていない。たとえそうなったとしても、その分野は長期的には多数のコンソーシアムチェーンの接続が一番システムコストが低いのでそちらに流れるのでは?と言うのが個人の意見。常に最適なシステムがデプロイされる訳ではないので、そちらに流れない可能性もあると思うが、現状、発行者のいるRWAをPublic chainに流す理由はまだ規制が緩くグローバル単一市場に近いものを作れるからだと思われる。ビットコインの場合も似ているが、発行者がいるものに規制をかけるのと異なり、ノンカストディアルで新しい分散型アセットの送金に世界的な規制を入れるのは憲法議論に近いものがあり比較すると難易度がだいぶ高いように思われる。
そもそもコンピューターサイエンスの視点からSatoshiの発明が何かと言うことを見ると、それまで不可能と思われていた、出入り自由なノード集合でのコンセンサスの実現だ。それまで不可能だと思われていた前提に一定の時間内でのコンセンサスの実現が無意識的に含まれていたが、Satoshiは時間方向を無限に利用することにより100%のコンセンサスを諦めて99.9999....%のコンセンサスを実現することが可能であり、工学的にはそれで問題ないことを示した。それによってDecentralized, Trustlessな価値の発行と価値交換を可能にするシステムが出来上がったわけだけど、当然システムは非常に複雑だし維持し続けることが可能なのか正直分からない。価値の生成と価値交換を非常に巧妙に分散的に行うことで動作している。
全体をDecentralizedなものにするビジョンの元、発生発展してきたものに、集中した発行者のいるRWAを取り扱うことをメインの用途にすることの意味は自分には規制を超えたグローバル単一市場以上のものを感じないし、それも規制が確定すればCentralizedなシステムの方が良いのでは?と感じる。分散的でない価値を上記のシステムで動作させるのは工学としてのアーキテクチャ的には非常に無駄が大きい。そもそもSatoshiのコンピュータサイエンス的な発明を必須としないものが本当に世界に必要だとしたらなぜその発明の前にできていないのか?それは規制の問題のみなのでは?
全てのものが最適なテクノロジーで実装される訳ではないし、局所最適で社会実装されるものもあるので、ここら辺は10年後に答え合わせと言う感じか。ただ、テクノロジー最適目指しているのではないの?っていう個人的感情は残る。
まあ、いずれにしろ、現在のところ、貨幣材としてはビットコイン以外にコンペチタはいないのではというのがこのエントリで言いたいことの一つ。